はじめに
十数年の時を経て復刻された、MELBAのパウンドケーキ。
何世代にも渡って愛されてきたこのパウンドケーキが「ひととき」のお供になりますように。
ここで私とMELBAのパウンドケーキとの数奇な縁、復刻までの道のりをご案内します。
有限会社丸の内 代表取締役
橋口一知
喫茶メルバで過ごした週末
街のいたるところに喫茶店があった昭和の時代。西調布の商店街の一角にあった「メルバ」は地域の人々に愛される存在だった。
ガラスがはめ込まれた木製のとびらが開くと、鐘の音が鳴り、来客を知らせる。きれいなコテ跡が残る白い漆喰壁。毛足の長い布貼りの深く沈みこむ椅子。レンガが埋め込まれたアーチ型のカウンター。
その奥でコックコート姿の白髪交じりの店主が忙しなく手を動かしている。フライパンをあおる音。ケチャップとバターの香り。コポコポと音を立て並ぶサイフォン。
私は週末になると、父と二人でよくメルバを訪れた。父と店主は、日本の洋食文化の草分けとして名を馳せた名店「東洋軒」でともに過ごした仕事仲間の間柄。
私たちはいつも、邪魔にならないよう店の片隅で静かに座っていた。
レジ前にひときわ明るいショーケースがあった。普段は手作りのショートケーキやチーズケーキがきれいに並んでいたが、時折、無造作に積まれるものがあった。
淡い花柄模様の包装紙と金色のリボンで包まれた、数本のパウンドケーキだった。
「いつもは作ってない。時間があるとき、いくらかまとめて作るんだよ」
時々しか置かれていないそれを、地元のお客さんは目ざとく見つける。飛ぶように売れていくのを、私は目の前で見ていた。
メルバの店主は銀座の名店コックドールで修行をした後、父と同じ東洋軒に転職。その後、支店の責任者等を経て独立、店を構えた。お客さんの前では口下手で、ときおり見せるいたずらっぽい笑顔が魅力的な人であった。客が引けると客席にどかっと座り競馬新聞を広げ、父とはよく夜を徹して麻雀をしていた。
父もいち商売人として、店主の腕に絶対の信頼を置いていたのだろう。事あるごとにメルバに焼菓子やケーキを頼んでいた。
私は、そんな環境で、子供ながらにではあるが「本物」に触れていたのだと思う。メルバの味も、そのひとつである。

家族に欠かせなかったケーキ
3人兄弟の私たち家族は年に3回訪れる誕生日とクリスマスの日を楽しみにしていた。
「メルバのケーキ」が食べられるからだ。
丸くて大きなホールケーキ。気泡が入り、舌触りが感じられるしっとりとしたスポンジ。牛乳と砂糖でできていることが子供にもわかるクリーム。
行ったこともない「ガイコク」を想わせる味だった。
ある年の、弟の誕生日。いつもはメルバのケーキを持ち帰ってくる父が仕事の都合で立ち寄れず、急遽母が代わりのケーキを駅前のチェーン店で買ってきた。
いつもと違う包装紙を開け、口にした瞬間。みなが押し黙り、主役の弟は泣き出してしまった。
あの日以来、幸せなことに、わが家の食卓にはメルバ以外のケーキが並ぶことはなかった。
そのメルバ特製のパウンドケーキも、わが家に不定期にやってくる宝物だった。当時、中身はだいたいアーモンドで、たまにオレンジピールやレーズンが入っていた。
パウンドケーキを切り出す幅を見守る兄弟たちの顔。隆起した天面のクッキー地のような食感。四方の黄金(こがね)色のグラデーション。包装紙の匂い。
昨日のことのようにはっきりと覚えている。
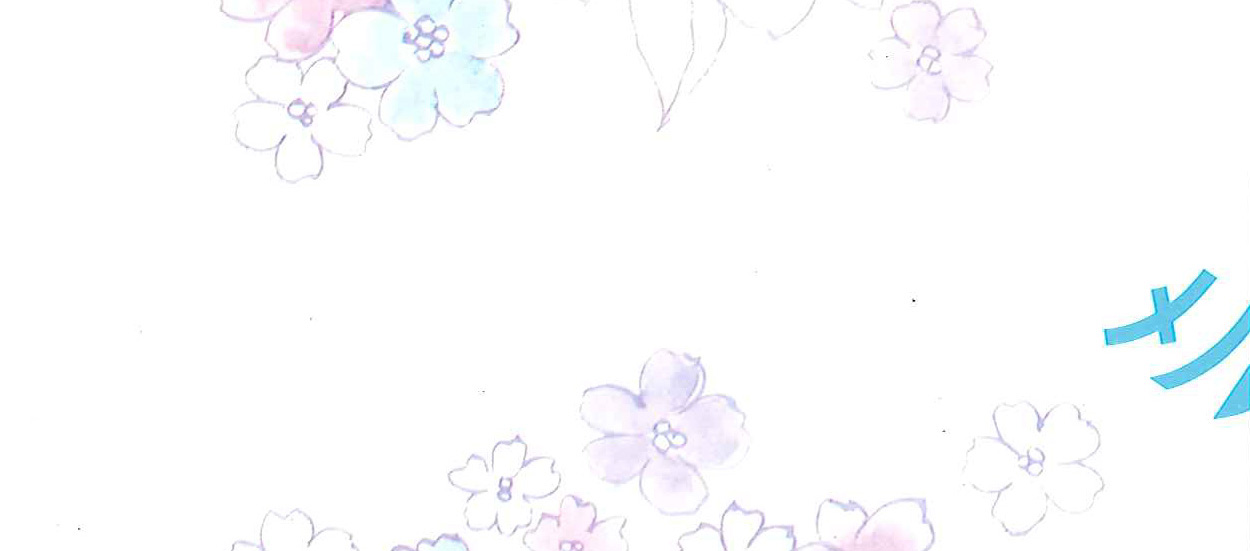
ないなら作る、今しかない
そんなメルバのパウンドケーキが食べられなくなって、15年の月日が経っていた。
私は記憶の中の味を求めて、気になるものを手当たり次第に買っては食べたが、ついぞ「この味だ」と思うものには巡り会えないままでいた。
中には近しいものもあったが、私の頭の中の記憶が邪魔をするのか、これというものを見つけることはできなかった。
「もう、あの味はどこにもないのかもしれないな」
半ば諦めかけていた中で迎えた2020年の春。
新型コロナウイルスが蔓延し、仕事は次々とキャンセル。長年セントラルキッチンとして入居していた建物が老朽化のため取り壊しとなり、新しい場所を探さねばならないという、泣きっ面に蜂のタイミングでもあった。
東京に季節外れの雪が舞った日、私は父に面と向かって頼み込んだ。
「メルバのパウンドケーキを復刻したい。やるなら今しかないと思う。一緒に手伝ってくれないか」

遺されていた気概と技術
メルバの店主が体調を崩し、父が西調布に通って店の手伝いをしたことがあった。
私はそこで雑務を手伝いながら、店主の一挙手一投足を見逃すまいとビデオカメラを回した。そのときの映像を何度も何度も見返してみた。
パウンドケーキを焼く、くたびれた窯。漏れ出す蒸気が滴り、厨房の床のタイルの目地を排水口に向かって伝う。画面の中の店主はタイルのひとつを指差しながら言った。
「このタイルの角を曲がったら窯の温度を下げる」
計量したのち、ボールに山のようになった粉。少量の塩を加えると、店主が一本の竹串を取り出してスッと立てる。
「仕込み中にお客さんが来て忙しくなってしまっても、後でわかるように目印をね」
バターはミキサーに投入する前に、その日の気温に合わせて柔らかさを調整する。店主は、四六時中沸かしてあるやかんの蓋を外し、そこにバターの塊が入った小さなボールを置く。客席に目を配りながら、手でゆする。
焼きの途中で窯のとびらを開けて、中の様子を見ながら、またもや竹串を取り出し、窯中央の一本に挿す。ゆっくり引き抜くと、自分の下唇と顎の境目辺りに軽く当てる。
「こうすると中の水分量がわかるんだよ」
惚れ惚れするふるまいだった。お客さまに良いものを出すという気概、そのために長年培ってきた技術。
街の喫茶店でここまでやるか。驚く場面がいくつもあった。
店主は「本物」を知っているだけに、いい加減なことができなかったのだろう。今になり、改めて思う。
一筋縄ではいかない再現
店主の奥さんからは、オリジナルのレシピを託されていた。
体調がすぐれなくなった店主が「ボケ防止だよ」といって、生まれて初めてワープロを使い、頭の中にあるレシピを書き出したものだという。
恐らく誰に見せるわけでもなかったそれは、一般の方にもわかりやすい平易でやさしい口調で綴られていた。店主の人柄が偲ばれる。
窯やミキサー等の機器もメーカーの方々にアドバイスをいただきながら、なんとか取り揃えることができた。原材料もレシピ通りのものを探したところ、製造元や内容までも同じものが奇跡的に現存していた。その費用を見積もったとき、本当に良い材料が使われていたことがよくわかった。
レシピ、同じ機器と原材料、そして一連の過程を録画した映像。父の支えもあり、条件はこれ以上ないほどそろってはいたが、それでも「あのパウンドケーキ」を完全に再現するには長い時間を要した。
新品の窯は暴れ馬のごとく元気が良すぎて、低い温度を保つのが難しい。生地のしっとり感を出すには水分量が必要だが、重視しすぎると生焼けになる上に、天面のカリッとした食感が出ない。
相反する状態を一本のパウンドケーキに併せ持たせるためには、焼成時の上火・下火温度の組み合わせを分刻みで調節するのはもちろん、ミキサー撹拌時点における温度管理も大切。
当日の気温や湿度にも左右される。膨張剤を使用しないため、背丈や食感など仕上がり具合はいつもやじろべえのように振れる。難しい。

過去と今がつながった瞬間
だが、味に関して迷うことは一切なかった。メルバのパウンドケーキを口にしたときの様々を、私は細かなところまで非常にはっきりと覚えていた。
試作開始から数か月後、試作品を包むラップに付いた油が細い川のような筋模様になっているのを見て、私は思わず声を上げた。
幼いころ、兄弟みんなで少しずつ大事に食べていたパウンドケーキを、丁寧にラップに包み円筒形のタッパーにしまっていた。その包みを開いたときに見ていた模様を思い出したのだ。
慌てて口に入れたそれは、とうとう、まさにあのメルバのパウンドケーキだった。
子供のころ、次はいつ食べられるのかと待ち遠しかったパウンドケーキ。人生の折り返し地点を過ぎた今、思いもよらぬことに、その宝物を自らの手で誰かに届けられるようになっていた。
そして現在、メルバの店主と同じように、窯の取手に手をかけながら焼き上がる一本一本を注意深く見つめているのは、あの、いつもと違う誕生日ケーキに泣き出してしまった弟である。
私たちの記憶の奥底にずっと沁みこんでいたメルバのパウンドケーキと、それがもたらしてくれた幸せな時間の長い余韻。
焼き上がりの甘い香りに、喫茶店のキッチンに立つ店主の後ろ姿をふと思い出しながら、一本のパウンドケーキをめぐる物語をつなぐことができた喜びを、今、静かに噛みしめている。

